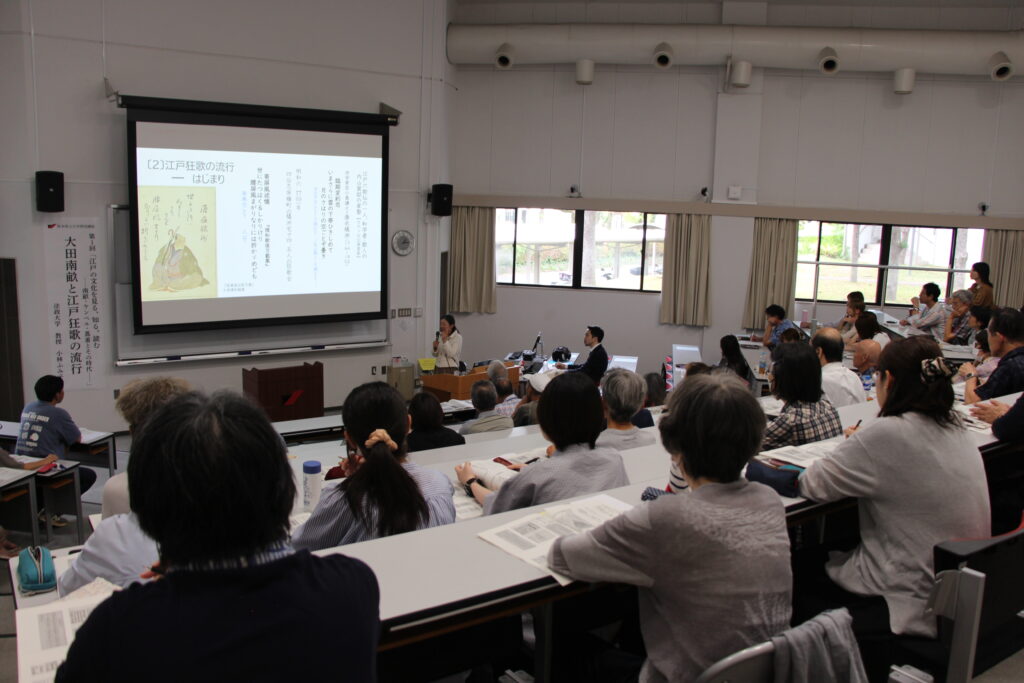本学文学部は、江戸時代の文学・文化の魅力や特色の紹介を趣旨として、3 名の専門家を講師とする公開講座を企画し、その第1回目を10月4日(土)に開催致しました。71 名の参加者があり、10 名の本学学生以外は、幅広い年齢層の方々にお集まりいただきました。
講師は法政大学の小林ふみ子教授。近世文学を専攻され、特に天明狂歌やその主導的立場にあった大田南畝(おおたなんぽ)の研究の第一人者であり、今回も「大田南畝と江戸狂歌の流行」と題してお話しいただきました。
講演では、狂歌の歴史から説き起こした上で、天明狂歌流行の源が南畝が学んだ内山賀邸の門にあったことを指摘。その門人の一人、小島謙之(狂名、唐衣橘洲、田安家家臣)の狂歌を例に、その雰囲気を説明されました。
続いて南畝が実は幕臣であり、漢学を修めた優秀な人物であったこと、18 歳の時にすでに漢詩用語集『明詩擢財(みんしてきざい)』を刊行し、翌年の狂詩集『寝惚(ねぼけ)先生文集』が文壇へのデビューであったというように、その教養の根幹に漢詩文があることが説明されました。
その上で、狂歌作者四方赤良(よものあから)としても頭角をあらわしてゆく様子を、多くの作品の鑑賞を通して丁寧に解説され、その本質に門付け芸「万歳」に通じる「めでたさ」があること、狂歌流行に蔦屋重三郎が大いに関わっていたことなどの指摘があり、その具体例として極めて美麗な多色刷り狂歌絵本『画本虫撰』・『潮干のつと』(いずれも蔦屋版)などを例示し、その高度な出版技術についても触れられました。
講演後は出席者との質疑に応じられ、先生のお気に入りの狂名(駄洒落に満ちた狂歌師達のペンネーム)が明かされる一幕もあり、盛況の内に閉会致しました。