令和5年(2023年)11月15日(水)、共通科目「新熊本学:ことば、表現、歴史」の特別講義を本学小ホールで開催しました。
講師は、本学客員教授であり、熊本日日新聞編集局長やテレビくまもとでニュース解説委員を務められた平野有益先生です。今回は、「火山と草原 世界文化遺産を目指す阿蘇」をテーマに、多角的な視点から御講演いただきました。
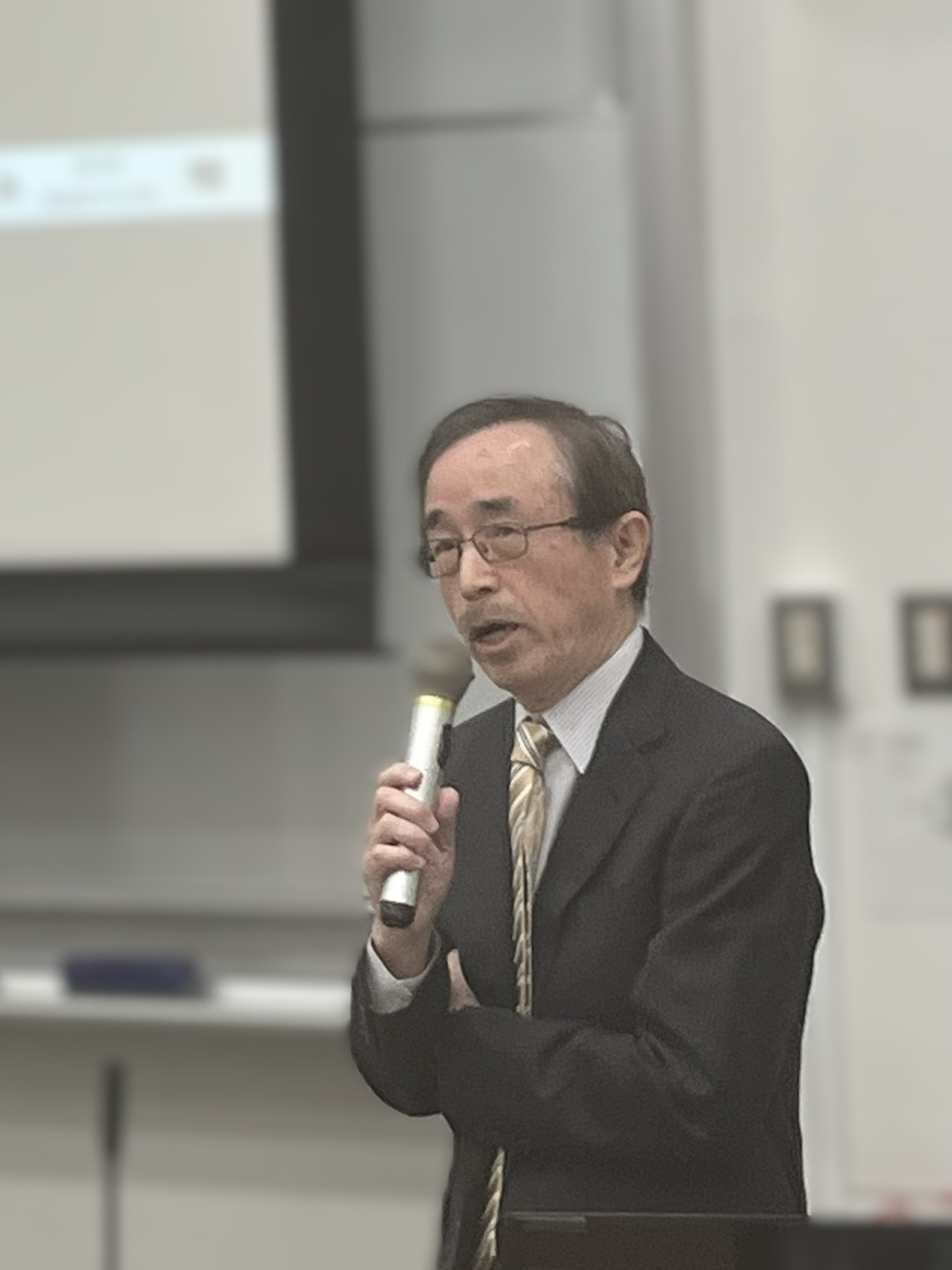
阿蘇の地理的概要の説明から講義が始まり、スクリーンには、阿蘇を模した細川流盆石、昔の絵地図、四季折々の表情を見せる阿蘇の写真など、阿蘇の風景が映し出され、それらを眺めつつ、観光と噴火災害の歴史の話題に入っていきました。
観光については、「明治時代には既に観光地として認知されていたこと、大正5年(1916年)の肥後大津~立野間を皮切りに鉄道が整備され昭和9年(1934年)12月に国立公園の指定を受けたこと、大観峰は熊本出身のジャーナリストである徳富蘇峰によって名付けられたことなどを紹介されました。一方で、「危険と隣り合わせの山」でもあるとして過去の噴火災害を例に挙げ、単なる天災ではなく人災としての側面も持つとも語られました。
次に、阿蘇を代表的な風景である「草原」について、「風が火を起こして、火が風を起こして人が亡くなってきたという歴史があるが、悲しみを込めた炎ともいわれる野焼きや、草原の造園師ともいわれる赤牛によって草原を守ってきた一方で、現在は農家だけでは草原は守れない、草原は美しいというだけでは済まされない状況が訪れている」と、草原維持問題の深刻さも語られました。

また、「北阿蘇の大シンボルが火口なら、精神的支柱は阿蘇神社である」「以前は裏阿蘇と呼ばれた南阿蘇は、開発が進んで今や人気観光地の一つとなっている」として、具体例を挙げながら、「人の営みと一緒になって、美しい景観が保たれていることを考えてほしい」とも訴えられました。
最後に「10年前に世界農業遺産になり、世界文化遺産、世界自然遺産登録に向けた活動が本格化している。野焼き、阿蘇神社、阿蘇五岳、豊後街道、草原といった財産はあるが、豊かな自然を維持するという人々の営みにより維持されてきた景観とその営みそのものが大事であり、新しい視点での価値づけが必要」とし、「最後の最後は、地元の人が地域の人が地元のことをどれだけ知って誇りを持っているかが肝になる」「風景を通して地域を見直していくことが大事」と締めくくられました。
本講義は、身近な地域である阿蘇の自然と歴史、現在の課題、未来に向けた展望について、深く考える貴重な機会となりました。









